あ行
赤ドラ
他の牌の色と異なり赤色になっている牌のこと
一般的には5の牌で用いられ、ドラとして扱われる
近年は4人打ちでは5の牌に1枚ずつ、3人打ちでは5の牌全てが赤ドラであることが多い
アタマ
アガりに必要な手牌の中の同じ牌2枚のこと
正式名称は雀頭(じゃんとう)
頭はね
2人以上のアガりが同時に発生した場合にアガり者を1人にするルールのこと
この際のアガり者は、放銃者からツモ番が1番近い人がアガりとなる
後付け(あとづけ)
副露して2つ目以降で役を確定させること
アリアリ
麻雀のルールで喰いタンと後付けが両方ありのこと。
ネット麻雀や4人打ち、関東での3人打ちでは一般的。
雀荘でアイス(ホット)アリアリと店員さんに注文すると、アイス(ホット)コーヒーに砂糖とミルクが入った飲み物が出てくる。
ちょっと通ぶれる。
暗槓(あんかん)
槓の種類。
自分の手牌に同じ牌を4枚揃えて他家に牌を全て見せて槓の発声をすること。
暗刻(あんこ)
鳴かずに同じ牌を3枚そろえた刻子(こーつ)のこと。
鳴いて3枚そろえると明刻(みんこ)という。
安全牌(あんぜんぱい)
安牌(あんぱい)ともいう。
他家に対して必ずロンされない牌のこと。
筋や壁は安牌ではなく比較的通りやすい牌なので注意。
上級者ほど安牌と比較的通りやすい牌の差ははっきりしている。
一向聴(いーしゃんてん)
聴牌の1つ手前の状態のこと。
一発消し(いっぱつげし)
立直後に立直者以外が鳴き(ポン・チー・槓)もしくは暗槓をすることで立直者の一発の役を消すこと。
裏ドラ(うらどら)
立直で和了った際に増えるドラのこと。
ドラ表示牌の下の牌がそれに該当する。
オーラス
その半荘もしくは東風戦の最後の局のこと。
降り打ち(おりうち)
自分が降りているつもりで放銃すること。
降りる(おりる)・オリ
自分が和了れないと判断して、相手に放銃しない牌を捨てて自分の和了を目指さない行為。
か行
客風牌(かくふうはい)
自風でも場風でもない役にならない字牌のこと。
オタ風ともいう。
風牌(かぜはい)
麻雀で使われる東南西北の牌のこと。
数え役満(かぞえやくまん)
和了時に13翻以上の役が揃った場合に適用される役満。
関西3麻では14翻からのルールもある。
片和了り(かたあがり)
聴牌時の待ち牌一部でしか役が付かずアガることができない状態のこと。
これが禁止されているルールもあり、後付けなしと言われる
壁(かべ)
特定の牌が複数枚見えている状態のこと。
同じ牌の見えている数が多いほど、その外側の牌では放銃しにくくなる。
上家(かみちゃ)
自分の左隣に座るプレイヤーのこと。
空切り(からぎり)
ツモった牌と同じ牌をそのまま捨てずに、既に持っていた牌を切ること。
河(かわ)
捨てた牌が並んでいる場所のこと。
嵌張(かんちゃん)
1つ飛びの数牌を持っていて間の数牌を待っている形のこと。
46の萬子の塔子がある時の待ちを嵌5萬という。
槓子(かんつ)
同じ牌を4枚揃える状態のこと。
他家に4枚見せることで刻子と同じ扱いになり、1枚ツモることができる。
槓するとドラが増えるルールが一般的。
発声は槓。
槓ドラ(かんどら)
槓が入ることで新しく増えるドラのこと。
危険牌(きけんはい)
他家に放銃する確率が高い牌のこと。
供託(きょうたく)
立直等で場に出されている点棒のこと。
局(きょく)
麻雀の1ゲームの単位。
喰い替え(くいかえ)
完成メンツのうち2枚を使って他家の捨て牌を鳴き、直後に残りの1枚を捨てること。
多くのルールで禁止されている。鳴いた牌と同じ牌だけでなく、スジの牌も喰い替えになるので要注意。
喰い下がり(くいさがり)
鳴くことで役の翻数が下がること。
愚形(ぐけい)
両面以外の待ちになる形のこと。
嵌張・辺張・シャンポン・単騎待ちのことを指す。
対義語 良形(りょうけい)
形式聴牌(けいしきてんぱい)
和了ることはできないが聴牌になっている状態のこと。
聴牌なので、流局すれば聴牌料はもらえる。
ケイテンと略す。
現物(げんぶつ)
そのプレイヤーの河にある牌もしくは立直後に一度通った牌のこと。
そのプレイヤーからは必ずロンされない。
刻子(こーつ)
同じ種類の牌を3枚集めてできる面子のこと。
鳴かずにできると暗刻(あんこ)鳴くと明刻(みんこ)という。
荒牌平局(こうはいへいきょく)
流局のこと。
孤立牌(こりつはい)
ターツになる前の何とも引っ付いていない牌のこと。
誤ロン・誤ポン・誤チー・誤カン
誤ってロン等の発声をしてしまうこと。
何かしらのペナルティが発生する場合がある。
ネット麻雀では起こらない。
さ行
三元牌(さんげんぱい)
白・發・中3種の牌の総称。
散家(さんちゃ)
子どもの総称。
三麻(さんま)
3人麻雀のこと。
差し込み(さしこみ)
意図的にと放銃しようとする行為。
洗牌(しーぱい)
流局後に牌を混ぜる行為のこと。
同じ字で牌を掃除することを洗牌(せんぱい)という。
仕掛け(しかけ)
鳴いて和了りに向かう行為のこと。
自風牌(じかぜはい)
風牌の中で自分の座席に応じた役牌のこと。
東家なら東・南家なら南が自風牌になる。
地獄単騎・地獄待ち・じごたん(じごくたんき・じごくまち)
1枚しか待ちがない単騎待ちのこと。
沈みウマ(しずみうま)
終局時基準の点数を満たしていないと減点されるウマのこと。
関西3麻でよく使われる。
日本プロ麻雀連盟のルールでも採用されている。
絞る(しぼる)
自分に必要はないが相手に鳴かれそうな牌を捨てないこと。
下家(しもちゃ)
自分の次の手番の人のこと。
西入(しゃーにゅう)
場が西になること。
順位ウマ(じゅんいうま)・ウマ
ゲームが終了した際に順位によって加わる点数のこと。
雀魂は5-15の順位ウマ。
1位:+15,000 2位+5,000 3位:-5,000 4位:-15,000
順子(しゅんつ)
連続した3つの数牌でできる面子のこと。
雀荘(じゃんそう)
麻雀屋さんのこと。
向聴(しゃんてん)
聴牌までの距離のこと。
後1つで聴牌の場合は一向聴という。
シャンポン
対子2種のどちらかで和了できる待ちのこと。
シャボ待ちともいう。
雀力(じゃんりょく)
麻雀の実力のこと。
雀暦(じゃんれき)
麻雀の経験数のこと。
少牌(しょうはい)
牌が足りていない状態のこと。
生牌(しょんぱい)
まだ1枚も見えていない牌のこと。
筋(すじ)
両面待ちに放銃しない牌のこと。
愚形の待ちには放銃することはある。
筋引っ掛け(すじひっかけ)
立直前に捨てた牌もしくは立直宣言牌の筋で放銃する愚形待ちのこと。
特に立直宣言牌の筋で放銃する時はモロ引っ掛けという。
スッタン
四暗刻単騎のこと。
セット雀荘
お客側が面子を揃えて卓を貸してくれる専門の雀荘のこと。
染め手(そめて)
混一色や清一色のような一色で構成されている手牌のこと。
た行
塔子(たーつ)
面子の1つ手前の段階の牌のまとまりのこと。
多牌(たーはい)
牌が多い状態のこと。
他家(たちゃ)
自分以外のプレイヤーのこと。
タテホン
門前の混一色のこと。
フリー麻雀でよく聞く。
打牌(だはい)
牌を捨てる行為のこと。
ダブドラ・ダブケン
牌1枚でドラ2個分の効果がある牌のこと。
5がドラの時の赤牌が頻出。
ダブロン
2人同時にロンが起こること。
黙聴(だまてん)
またの名を闇聴(やみてん)。
聴牌したが、立直をかけないでいること。
多面張(ためんちゃん)
待ち牌が3種以上の待ちのこと。
単騎(たんき)
七対子の待ちのように1枚持っている同じ牌で雀頭などができる待ちのこと。
吃(ちー)
上家から捨てられた牌で順子ができる時に、その牌を鳴く時にする発声。
起家(ちーちゃ)ゲームスタート時、東家スタートの場所のこと。
吃聴(ちーてん)
チーして聴牌になること。
ちーして一向聴のときは吃向聴(ちーしゃんてん)という。
中張牌(ちゅんちゃんぱい)
数牌の中でも特に2〜8の牌のこと。
チョンボ
ミスをしてペナルティをもらうこと。
ネット麻雀では起こらない。
遅ロン・遅ポン(ちろん・ちぽん)
ロンやポンの発声が遅れること。
特にポンは遅れるとチーと被ることがあるので即座にポンするのが望ましい。
自摸(ツモ)
山から牌を引く行為のこと。
自摸で和了ることを自摸和(つもほー)という。
自摸切り(つもぎり)
ツモった牌を捨てること。
手替わり(てがわり)
牌を入れ替えることで打点や待ちがよくなる牌のこと。
手出し(てだし)
ツモ牌以外の手牌の中から牌を捨てること。
手なり(てなり)
特に役を狙ったり打点を狙ったりせず和了りに1番効率の良い方向へ進めること。
聴牌(てんぱい)
後1枚有効牌を引くもしくは他家から捨てられることで和了することができる状態のこと。
門前の場合は立直することができる。
点跳ね・符跳ね(てんぱね・ふはね)
麻雀の点数で符が大きくなり、和了り点が大きくなること。
点棒(てんぼう)
麻雀の得点を表す棒のこと。
点棒状況(てんぼうじょうきょう)
他家との点数差などの点数状況のこと。
対子(といつ)
同じ牌2つ1組のターツのこと。
対子落とし(といつおとし)
対子の牌を捨てる行為のこと。
手出しかツモ切りかはかなり重要。
対面(といめん)
自分の向かいの座席のプレイヤー。
同順(どうじゅん)
自分の手番が終わってからもう一度回ってくるまでのこと。
トッパン
倍満のこと。
大阪・3人麻雀でよく聞く。
トップ目
現状トップのプレイヤーのこと。
飛び
点数が0以下になりゲームが終了すること。
終わらないルールもある。
東発(とんぱつ)
東一局のこと。
東風戦(とんぷうせん)
東場のみで終わるルールのこと。
東ラス(とんらす)
東四局のこと。
な行
中膨れ(なかぶくれ)
3445のように順子の真ん中の牌を2枚持ってる形。
2面子できやすく、両面待ちになる良い形。
南入(なんにゅう)
場が南になること。
ノーテン
聴牌していない状態のこと。
ノーテン罰符(のーてんばっぷ)
流局時にノーテン者が聴牌者に支払う点数のこと。
は行
八連荘(ぱーれんちゃん)
同じプレイヤーが8局連続で親になること。
8回目に和了ることで役満になるルールもある。
牌効率(はいこうりつ・ぱいこうりつ)
効率よく和了りや高打点に向かう理論のこと。
牌譜(ぱいふ)
麻雀をした記録のこと。
ネット麻雀では当たり前に記録されており見ることができる。
場風牌(ばかぜはい)
風牌なら中で場に応じた役牌のこと。
東場なら東・南場なら南が場風牌になる。
バカホン
鳴いて混一色のみの手牌のこと。
場況(ばきょう)
他家の捨て牌や手牌の状況。
半荘戦・東南戦(はんちゃせん・とんなんせん)
東場と南場の2周行うルールのこと。
近年の主流のルール。
平場(ひらば)
0本場のこと。
副露(ふーろ)
鳴きの総称。
フリー雀荘
1人でお店に行っても麻雀ができるお店のこと。
お客同士で麻雀をすることもあれば、店員が数合わせで入って麻雀をすることもある。
振聴(ふりてん)
聴牌しているがロンできない状態のこと。
自分が捨てている牌が待ちの時、立直後に見逃した時、同順で見逃した牌は振聴になる。
ベタオリ
和了りには向かわず手牌を崩し放銃しないように立ち回ること。
辺張(ぺんちゃん)
12や89の数牌を待っていおり、1種の数牌で順子(しゅんつ)ができる形のこと
和了(ほーら)
アガりのこと。
放銃・振り込み(ほうじゅう・ふりこみ)
自分の捨てた牌で他家にロンされること。
棒聴即リー(ぼうてんそくりー)
役や打点を狙わず、塔子選択もせずに聴牌したらすぐに立直すること。
碰(ポン)
対子の牌を持っている時に他家が捨てた3枚目の牌を鳴く際にする発声。
碰聴(ぽんてん)
ポンして聴牌になること。
ポンして一向聴のときは碰向聴(ぽんしゃんてん)という。
ま行
回し打ち(まわしうち)
他家に放銃しにくい打牌をしながら和了りに向かう行為。
かなりの技術が必要。
見逃し
和了り牌を意図的に見逃し和了らないこと。
明槓(みんかん)
槓の種類。
自分の手牌に同じ牌を4枚揃えずに槓子を作ること。
暗刻から他家が捨てた牌を槓することを大明槓(だいみんかん)、ポンした後に4枚目の牌を手牌から槓することを加槓(かかん)という。
明刻(みんこ)
鳴いて同じ牌を3枚そろえた刻子(こーつ)のこと。
鳴かずに3枚そろえると暗刻(あんこ)という。
無筋(むすじ)
立直や仕掛けに対して通っていない危険な牌のこと。
無駄ヅモ
自分の手牌が進まないツモ牌のこと。
門前(めんぜん)
鳴いていない状態のこと。
門前で聴牌すると立直することができる。
メンタンピン
立直・断么九・平和3種の役の略称
メンバー
雀荘の店員のこと。
徐々に使われなくなってきた。
盲牌(もうぱい)
牌を見ずに手で触った感触で牌の種類を判別すること。
や行
么九牌(やおちゅうはい)
数牌の中でも特に1・9牌のこと。
焼き鳥
一度も和了ることができずに終局すること。
闇聴(やみてん)
またの名を黙聴(だまてん)
聴牌したが、立直をかけないでいること
有効牌(ゆうこうはい)
自分の手牌の向聴数が1つ進む牌のこと。
向聴数は進まないが受け入れ枚数が増えたり、形がよくなる牌のことを2次有効牌という。
4麻(よんま)
4人麻雀のこと。
ら行
ラス親
自分の最後の親もしくはオーラスの親のこと。
ラス牌
山に残っている最後の牌のこと。
ラス半(らすはん)
この半荘で終了すること。
雀荘で使われる用語。
店員に伝えて終わることが望ましい。
理牌(りーぱい)
手牌の中を並べること。
両面(りゃんめん)
56のように連続した数牌の塔子で両端2種で順子ができる待ちのこと。
56萬を持っているときは47萬待ちという。
流局(りゅうきょく)
正式名称は荒牌平局(こうはいへいきょく)。
誰も和了らずに局が終了すること。
聴牌いているとノーテンの人から点数がもらえる。
嶺上牌(りんしゃんはい)
槓してツモることができる牌のこと。
良形(りょうけい)
両面以上の待ちの形のこと。
対義語 愚形(ぐけい)
連荘(れんちゃん)
同じプレイヤーが親を続けること。
栄和(ろんほー)
他家が捨てた牌で和了ること。
わ行
王牌(わんぱい)
ドラ表示牌を含めて誰もツモることができない14枚の牌のこと。
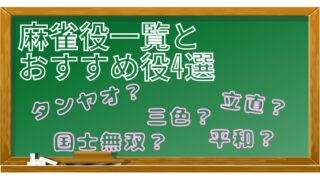
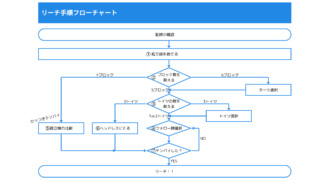
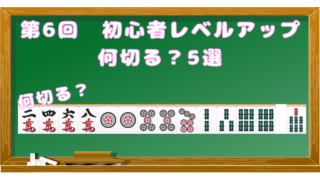
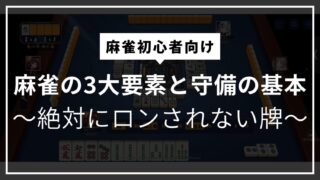
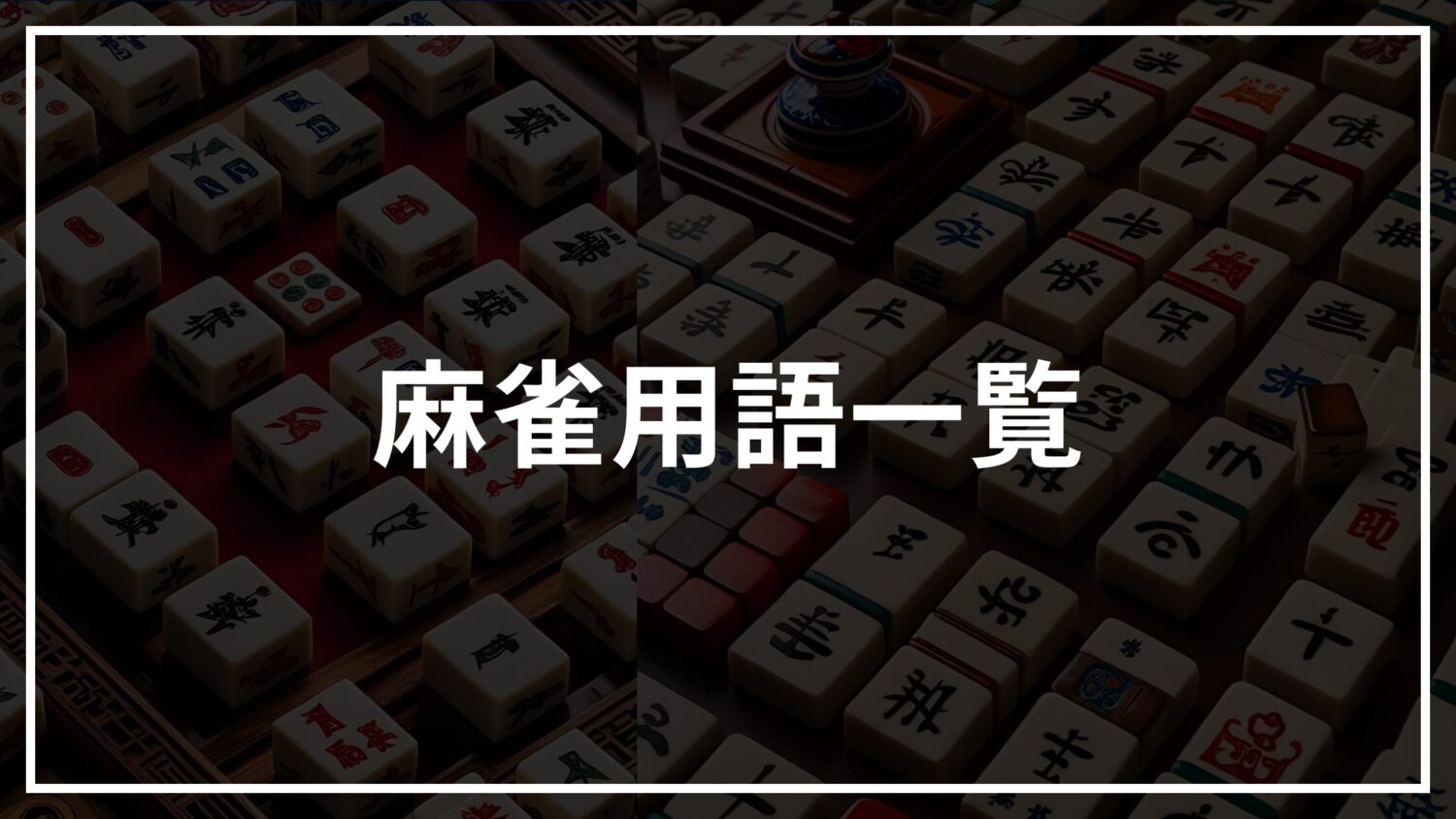
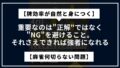
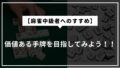
コメント